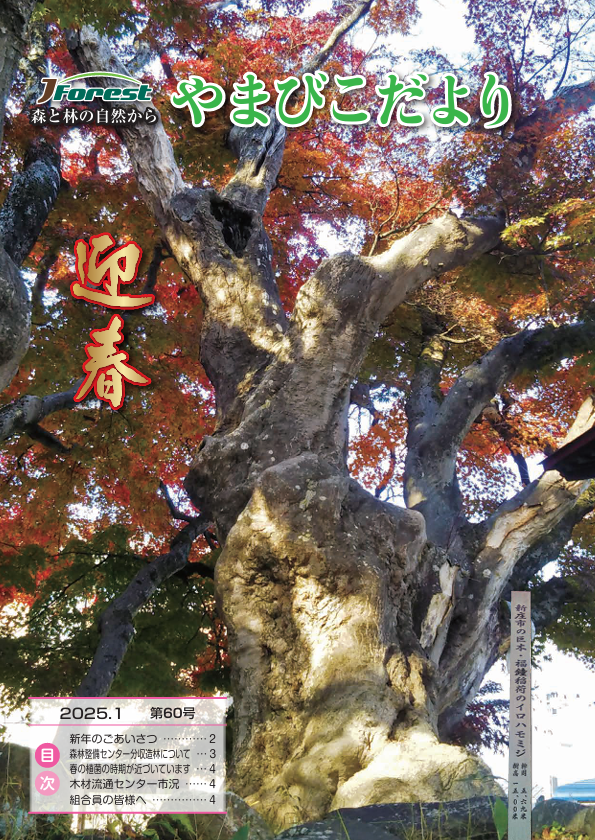
謹んで新年のお慶びを申し上げますとともに、組合員各位に於かれましては、日頃から森林組合の活動に対しまして、深いご理解とご協力を賜りまして、改めまして感謝と敬意を表するものであります。
昨年を振り返れば、元旦の能登半島地震が最大震度7という大被害が発生し、多くの方々が被災され、亡くなられた方もいらっしゃる災害でもありました。重ねて7月25日に発生した大雨の被害は、庄内・最上を中心に、甚大な被害をもたらし、ここ最上郡では、鮭川村や戸沢村で住民の避難や集団移転など100年に一度の災害とは言え、今まで築いてこられた生活を一変された方々もいらっしゃいました。これらに対して心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。
林業関係に於きましても、林道の崩壊によって作業が不可能になり、また、大幅な遅れや土砂崩れなどによって倒木となり、水田や側溝に流れ、耕作不可能状態になりましたが、これらの支障木の伐採等を実施し仮復旧に貢献致しました。その他にもショッキングな話題としては、消滅可能性のある自治体が七四四あり全体の四割にあたるというニュースや去年の出生者数が75万人余りで過去最低となったニュースでありました。少子高齢化は益々歯止めがかからず、我々、中山間地に住み地域を守って行こうとする団体には課題の大きすぎる問題でした。
しかしながら、その中にあって、県土の約七割を占める豊かな森林資源を有効に活用しながら、林業及び木材産業を活性化して雇用の創出と地域活性化につなげていく事が、我々に出来うる大きな仕事であると認識しております。
近年は、山地災害が激甚化・頻発化しておりますが、森林の多面的機能や水源涵養・山地災害の防止、地球温暖化の防止などの役割について再認識しております。
こうした状況の中、森林資源の循環利用と森林の保全を図る「やまがた森林ノミクス」を推進し、新しい技術であるICTの活用等によって施業の安全性や生産性を高め森林の適正な管理と持続可能な林業の実現に取り組んでおります。
さて、以前から譲与税の配分見直しについて系統あげて運動し、より山側に配分できるようにという事を要望して参りましたが、関係各位のおかげで、私有林人口面積が五五%・林業就業者数が20%・人口が25%に変更になりました。森林経営管理制度については、県・市町村と連携を図りながら、各保育事業の嵩上げ等森林整備に有効に使って頂けるように提案していける体制を作って行かなければと考えております。
先だって、役員研修において、秋田県能代市工業団地に進出した中国木材を視察させて頂きました。現在は、24万㎥の原木を扱い4m3m2mの原木を仕入れておりますが、順調に集荷されていて、近い将来に発電を計画しているとのことでした。我々も川上として、原木の安定供給が求められており、そのためにも「伐ったら植える」の「やまがた森林ノミクス」の一層の推進のために再造林を積極的に推進し、また、その後の保育の分野においても所有者負担なしで、資源が循環していくスキームを構築していかなければなりません。また、素材生産においても、高性能林業機械の導入や人材の育成に力を入れ、農林大学校や農林専門職大学の実習のフィールドを提供しながら共に人材の育成に繋げて行こうと思います。今、若い活気のある人材は、林業界の希望の星であります。
将来の林業の再生にも大きく貢献できるように、就労環境の整備など必要な制度全体を整備し受け入れていかなければなりません。
最後に、再度、適正な立木価格について申し上げたいと思います。昨年もこの紙上をお借りして述べさせて頂きましたが、木材価格は、現在、市場逆算方式になっております。つまり、各流通段階から経費と利潤を控除して丸太価格が決定しており、さらに、伐採・搬出・運搬を控除して立木価格が決定しております。一般的には、資材の高騰や人件費の高騰などの経費の上昇分を価格に転嫁しているのが現状であります。
森林は多面的機能を発揮し地球温暖化など大きく環境に寄与しております。しかしながら、今の立木価格では、持続可能な林業の経営は難しく森林経営の放棄や組合員離れは益々増加し、森林は、負の遺産として引き継ぐものがいなくなってしまうのではないかと危惧しております。今後、森林吸収源対策や花粉症対策として伐採や再造林が進んで行くときに、より循環していくためにも合理的な価格形成の議論は、早急に結論が欲しいと思っております。是非、組合員の皆様も後押しお願いいたします。
このように、森林の重要性は将来に向けて益々増大して参ります。
令和七年も、組合員の皆様とともに林業の再生と地域の活性化に向けて取り組んで参りますので、よろしくご指導頂きますようお願い致しまして、年頭のご挨拶と致します。
2025.1
最上広域森林組合 代表理事組合長
佐藤 景一郎


